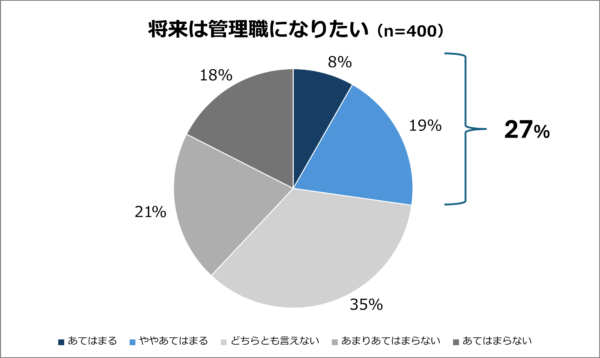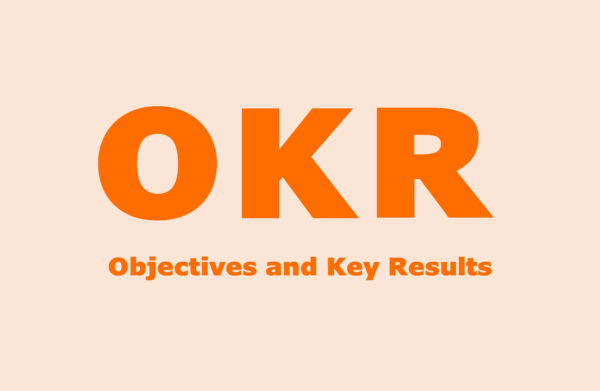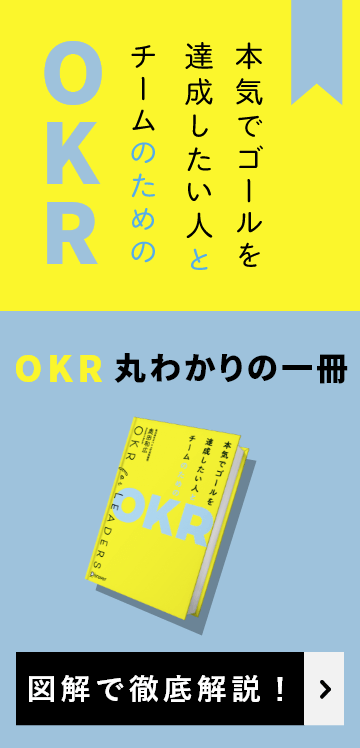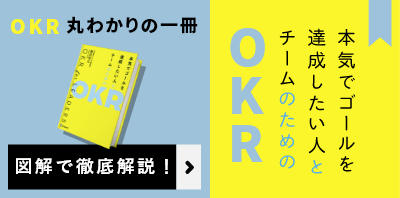経営者や人事部門にとって、従業員のエンゲージメント向上は重要な課題です。社員の意欲や満足度が高まれば、生産性の向上や定着率の改善につながるため、どの企業にとっても無視できないテーマでしょう。
本記事では、エンゲージメントを高めるために「参加」を促進する重要性を解説します。特に、OKR(Objectives and Key Results)の活用によって、従業員の主体的な関与を促し、組織の成長につなげる方法を紹介します。
「参加」と「所属」の違いとは?
従業員と組織の関係性を考えるうえで、「参加」と「所属」という二つの概念を理解することが重要です。これらは似ているようで異なる意味を持ち、エンゲージメント向上の方針を決める際の鍵となります。
1. 参加
「参加」は、特定の目的のために意図的・一時的に組織やプロジェクトに関与することを指します。例えば、新規プロジェクトやタスクフォースに自ら手を挙げて参加することが該当します。この関わりは目的達成とともに終了することもあり、関係の深さは比較的浅いのが特徴です。参加には本人の意思が不可欠です。
2. 所属
「所属」は、組織やコミュニティと長期的な関係を築く状態を指します。所属することで安心感や仲間意識が生まれる一方で、責任やしがらみも伴います。たとえば、正社員として企業に所属することや、家族や地域コミュニティに属することがこれに当たります。
日本企業では「所属感」が重視されがちですが、現代の多様な働き方を考慮すると、必ずしも所属だけを強調するのが最適とは限りません。特に若い世代では、キャリアの選択肢を広げる意識が高まり、柔軟な「参加」の機会を求める傾向が強まっています。
エンゲージメント向上には「参加」を増やすことが鍵
エンゲージメントを高めるには、従業員が主体的に「参加」する機会を増やすことが効果的です。これにより、次のようなメリットが得られます。
1. 自律性と責任感の向上
「参加」は、従業員が自らの意志で組織活動に関わることを促します。このような環境では、従業員が自分の役割を明確に理解し、自発的に行動する意欲が高まります。
2. チーム目標達成による満足感
チーム目標への参加機会を提供することで、達成感を得やすくなります。これにより、従業員のモチベーションが持続します。
3. 柔軟な働き方への対応
チーム全体の業務や意思決定への参加機会を増やすことで、多様な価値観や働き方をサポートしやすくなります。これにより、従業員が自分の価値観、キャリア、ライフスタイルに合ったチームへの参加方法を考えることができます。
OKRが「参加」を促進する理由
OKR(Objectives and Key Results)は、組織目標と個人目標をリンクさせることで、従業員の「参加」を促進する強力なツールです。このフレームワークを導入することで、次のようなメリットが得られます。
1. 明確な目標設定
OKRは、「何を達成したいか」という目標(Objective)と、それを測る具体的な指標(Key Results)を定義します。このプロセスは、従業員が自分の役割を理解し、組織全体の目標とどのようにリンクしているかを把握する助けとなります。
2. 透明性とコミュニケーションの向上
OKRの設定プロセスには、従業員自身が関与することが求められます。この参加型のアプローチは、組織内の透明性を高め、上司と部下間のコミュニケーションを促進します。これにより、従業員は自分の貢献がどのように評価されるかを理解しやすくなります【9†source】。
3. チャレンジングな目標で成長を促進
OKRは、達成可能でありながら挑戦的な目標を設定することを推奨しています。これにより、従業員は自分のスキルを磨き、成長する機会を得られます。
4. 自律性と責任感の強化
OKRは、目標達成の方法を個々の従業員に委ねることで、自律性を高めます。このアプローチは、従業員が自分の仕事に責任を持ち、意欲的に取り組む環境を作り出します。
おわりに
エンゲージメント向上のためには、企業が従業員にどのように関わってほしいかを見直し、柔軟な「参加」の機会を増やすことが重要です。自律性やモチベーションを引き出し、組織の成長を加速させるためにも、「所属」だけでなく「参加」を意識した施策を取り入れるべきでしょう。
その実現手段として、OKRは非常に有効です。明確な目標設定と透明性の高いプロセスを通じて、組織全体の「参加」を促進し、持続的な成長につなげていきましょう。