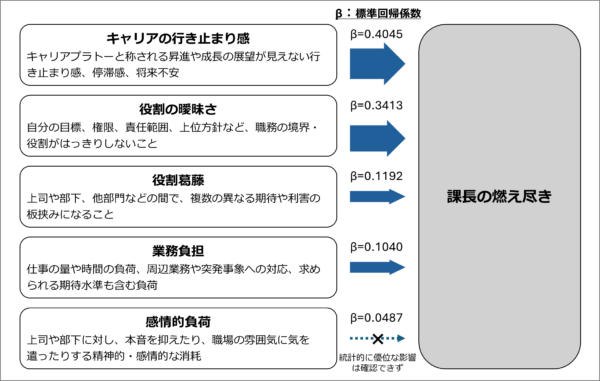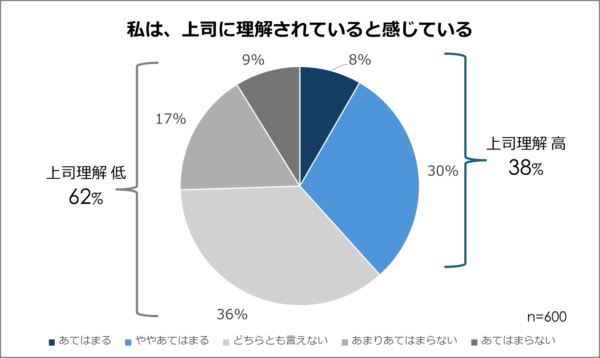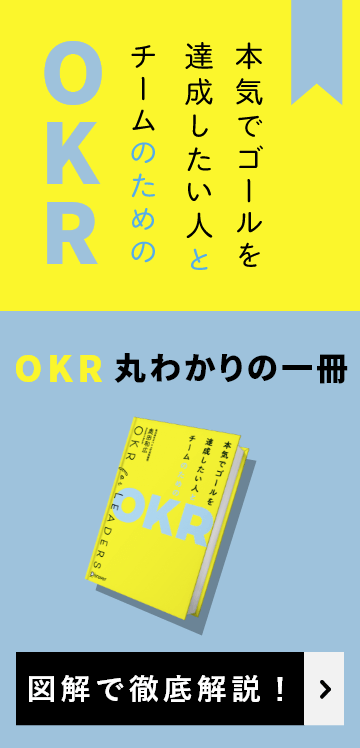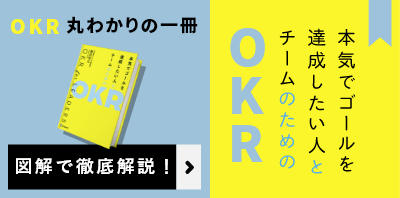四半期ごとのOKRレビュー会議は、事前に準備を整え、データも揃え、チーム全員で向き合う大切な振り返りの場です。導入当初は難しく感じる場合もありますが、回数を重ねると滞りなく実施できているようになっていきます。
一方で、慣れてきたタイミングで次のような物足りなさが生まれることも少なくありません。
「もっと未来につながる気づきがあるはずだ!」
「きちんとレビューはしているが、このままでよいのだろうか?」
こうした違和感、物足りなさは、実はチームが次のレベルに進化するチャンスです。
そこで今回は、「基本的なレビューは実施できている」状態から、チームがさらに強くなるためのレビュー会議の再設計について解説します。
OKRレビュー会議の3段階の再設計
| レベル | 目的 | 効果・ポイント |
|---|---|---|
| Lv.1 報告と共有の場 |
状況説明 現状確認 |
過去の事実整理、共有が中心。状況共有により透明性は高まりますが、新たな打ち手や学習にはつながりにくい。 |
| Lv.2 調整と改善の場 |
施策修正 再現性向上 |
行動レベルの改善、調整が進み、短期的には成果につながります。ただし、前提や仮説の見直しは起こりにくく、打ち手が小さくまとまりがちです。 |
| Lv.3 学習と進化の場 |
前提の見直し 仮説の更新 |
新たな発見や示唆が生まれ、前提認識や戦略がアップデートされる。組織としての学習能力が大きく加速します。 |
レベル1:報告と共有の場
このレベルでは、会議の大半が状況説明と事実確認に使われます。
透明性が高まり、認識のズレをなくす効果はありますが、議論は深まらず学習につながりにくいという限界もあります。
「情報共有のみで終わってしまう」
「過去の報告が中心で議論が起きない」
このような感覚がある場合は、まだレベル1に留まっている可能性があります。
レベル2:調整と改善の場
このレベルでは、行動や施策の調整・改善が中心になります。
- マニュアルを修正し、再現性を高める
-
時間・工数の使い方を改善する
といった「やり方」の改善が進みます。
短期的には効果が出やすく、手応えも感じられるでしょう。しかし、方針そのものは変わらず、前提や仮説には手つかずのままです。そのため、改善は進む一方で大きな飛躍が起きにくい状態です。
レベル3:学習と進化の場
結果が良かった、悪かったという結果そのものよりも、そこから得られる発見や示唆に焦点を当てる段階です。
-
想定していた顧客像は本当に正しかったのか
-
提供価値そのものは本当に響いていたのか
-
戦略の前提となるニーズが変化していないか
こうした問いを通じて、自分たちの判断基準や前提そのものを見直します。このレベルに進むと、新しい発想や戦略的な気づきが自然と生まれやすくなります。
KPTを学習モードにアップデートする
多くのチームはKPTをレベル2の改善ツールとして使っていますが、少し質を変えるだけでレベル3に近づけることができます。
| 区分 | 通常KPT | 学習視点をオンするKPT |
|---|---|---|
| Keep | 何がうまくいったか | どの前提が正しかったか/どの強みが成果につながったか |
| Problem | 何が課題だったか | どの前提がズレていたか/想定外の問題、反応は何だったか |
| Try | 次にどう改善するか | どの仮説を更新するか/何を再定義するか |
こうした問いをKPTに組み込むことで、振り返りが行動の改善だけで終わらず、前提・仮説の見直しにつながる学習モードへ自然に移行します。
また、KPTをこの形で運用すると、レビューの場が単なる報告会ではなく、チーム全体が思考をアップデートする対話の場に生まれ変わります。行動レベルではなく意味づけのレベルでの学習が進むため、次の四半期のOKRの質も向上します。
レベル3へ引き上げるためのアプローチ
まずは、場の目的を明確にしましょう。
単なる報告や改善ではなく、この3か月で私たちは何を学び、どう前提や仮説を見直すことで、飛躍的な成果を上げるための「学習と進化の場」だと、リーダーが明確に伝えます。
次に「想定外」「外れ値」は学びの源泉と捉えましょう。
失敗だけでなく、成功や反応など当初の想定と違った事象からこそ学習が生まれます。また、データや事象の中にある「外れ値」にも目を向けると価値ある発見につながることが多いです。
また、多様な視点を歓迎し、粒度の違いも許容しましょう。
KPTは多数のメンバーを巻き込んで多様な視点を活用することが重要です。そのため、書き方、内容、粒度などを細かく統一しすぎず、意見の幅を許容しましょう。どんな意見も否定せずに受け止めることで、多様な示唆が生まれます。
最後に、フォーカスに立ち返りましょう。
OKRの重要な原則である「フォーカス」に立ち返り、最も重要な学びと最優先の挑戦に全員で集中することで、OKRレビューは次の成功を生み出す「学習と進化の場」に生まれ変わります。